水災害による被害の低減に向けた取組み
1.「水災害への備え」、「ハザードマップ普及」等啓発活動
水災害による被害は「事前の備え」「事前の対策」により低減を!
地球温暖化等による自然災害の激甚化・頻発化、特に台風や梅雨前線、そして線状降水帯等に起因する集中豪雨・大雨等の水災害による被害が拡大しています。
日本損害保険協会では、リスクの担い手たる損害保険事業の業界団体として、保険金の迅速なお支払いによる復旧・復興の支援という社会的役割を発揮しつつ安全・安心な社会の実現に貢献するため、防災・減災に向けた各種取組みを強化しています。
特に、社会環境・自然環境の変化に適応した災害に強い社会の実現を目標に「行政と連携した強靭なまちづくりへの貢献」と「ハザードマップ等の普及促進」の施策を中心に取組みを行ってきました。水災害による被害には、「事前の備え」「事前の対策」による被害低減の取組みが重要です。
参考まで、各地における取組状況の一部をご紹介いたします。
例①:「あんどうりす」さんの水災害セミナーを YouTube で公開!(2023年1月13日)
※秋田で開催されたアウトドア防災ガイド「あんどうりす」さんの「水災害対策オンラインセミナー」の模様
例②: 国土交通省と連携したハザードマップ利活用講習会(2021年12月12日)
※島根県美郷町でハザードマップ/マイ・タイムラインの重要性、水害から生活を守るための制度・備え等を啓発
2.国土交通省「流域治水オフィシャルサポーター」制度
(1)認定団体への登録
激甚化・頻発化する自然災害、特に豪雨・台風等の水災害による被害の拡大を受け、国土交通省を中心に政府は、水害から国民の生命と暮らしを守るための新たな水災害対策である「流域治水」を掲げ、取組みを強化しています。
流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」においては、企業、団体等を含め多様な関係者の連携が不可欠であり、国土交通省は流域治水に資する取組を促進するため、2023(令和5)年3月に「流域治水オフィシャルサポーター」制度を創設し、趣旨に賛同し取組みを実践する企業・団体を募るべく呼びかけを行いました。
日本損害保険協会は、上記のとおり、水災害への備えの重要性やハザードマップの周知・普及そして事前準備・事前対策等の必要性の啓発に取り組んできたことを踏まえ、同制度への登録を申請し、同年6月30日付で、国土交通省から「流域治水オフィシャルパートナー」団体に認定されました。(下記掲載の認定証のとおり、2024(令和6)年度もオフィシャルパートナーとして認定継続中。)
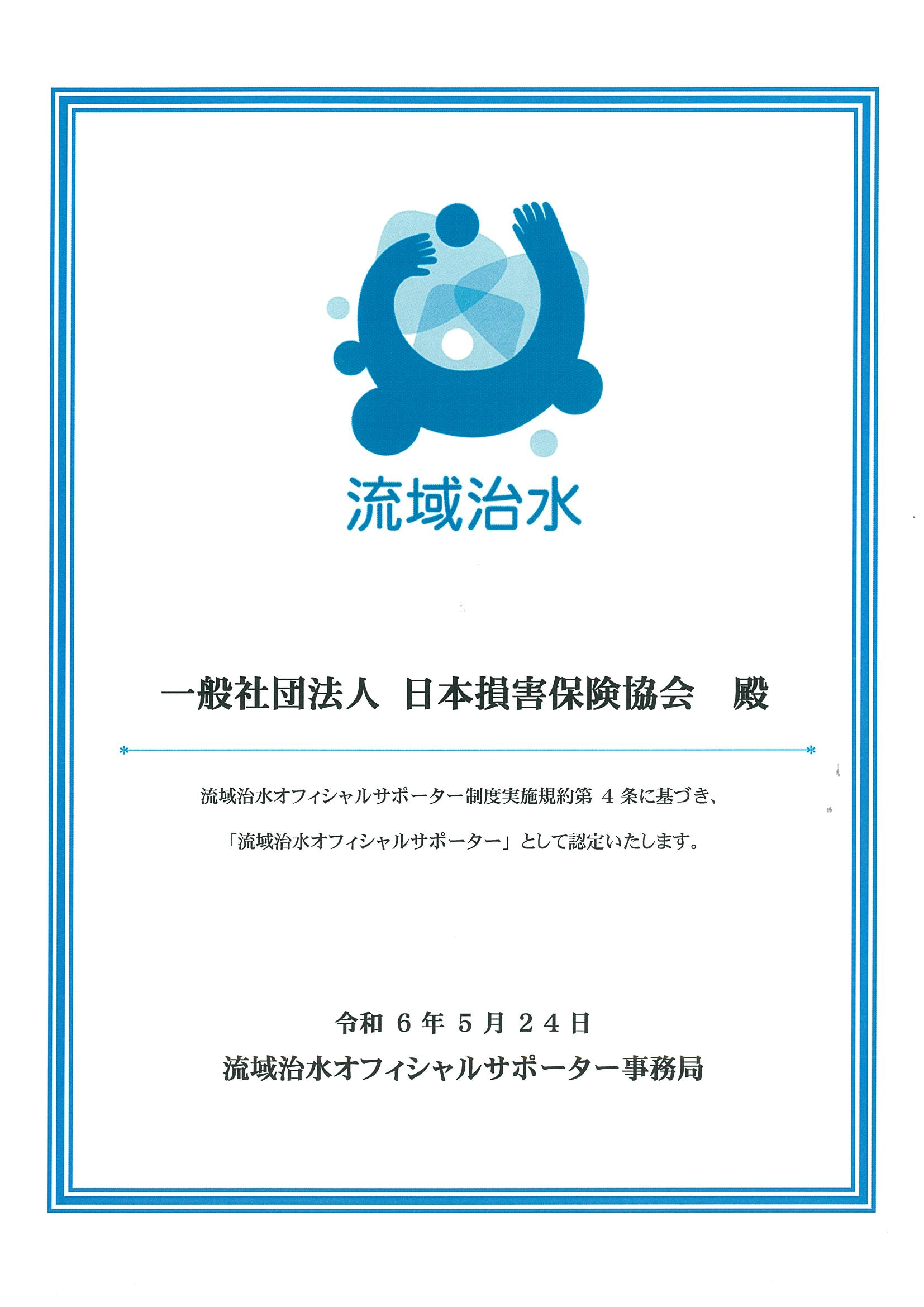
国土交通省Web 62企業・団体等を「流域治水オフィシャルサポーター」に初認定!~企業・団体等による新たな流域治水の普及・啓発の始動~
国土交通省Web「流域治水」ロゴマークを決定しました~流域のみんなが水害対策を取り組むきっかけに~
(2)認定団体としての取組み
●災害を振り返る講演会の実施
日本損害保険協会では、「流域治水オフィシャルサポーター」団体に認定されたことを踏まえ、この間も実施してきた水災害への備えの啓発を強化し、地域の方に直接呼び掛ける取組みを行っております。
一例として、日本損害保険協会の 新納 啓介 会長(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役社長)が直接、地域の方々に呼び掛けを行ったイベントを2件ご紹介します。
具体的には、2023(令和5)年8月2日に鹿児島県で開催した講演会「 8・6 水害から 30 年、改めて備えについて考える」と同年9月6日に岡山県で開催した講演会「西日本豪雨から5年、これからの防災まちづくりを考える」です。
両講演会とも災害を振り返り、改めて水災害への備え、教訓の活用を呼び掛ける目的で企画したものであり、全国地方新聞社連合会の協力のもと、鹿児島の講演会については南日本新聞社との共同主催、鹿児島県の後援、岡山の講演会については山陽新聞社との共同主催、岡山県の後援をそれぞれ仰ぎ、鹿児島県の塩田知事、岡山県の伊原木知事ご自身から、水災害への備え、ハザードマップの事前確認の重要性を訴えていただき、開催後は両新聞社紙面での採録記事掲載を通じて、地域のできるだけ多くの方に認識願うよう取組みを行っております。
講演会「8・6 水害から 30 年、改めて備えについて考える」を開催
講演会「西日本豪雨から 5 年、これからの 防災まちづくりを考える」を開催
●学校教育現場へのハザードマップ等の周知・啓発
学校の多くが災害時における緊急避難場所や避難所に指定されております。また、学校は多くの学生・生徒等が集う場所でもあります。
学校保健安全法では、学校の実情に応じて学校安全が図られるべきとされており、学校毎の「学校安全計画」策定を求めています。また、令和4年3月に通知された「第3次学校安全の推進に関する計画」においては、自然災害の多発および東日本大震災の教訓を踏まえ、地域の災害リスク等地域の特性に応じた教育訓練等の実施の重要性を強調しています。
このような中、日本損害保険協会では、教育現場における取組みの一助としていただくべく、2023(令和5)年8月21日に、一般財団法人 経済広報センターが実施する「教員の民間企業研修」の中で、東京大学准教授の 小田隆史 先生に「学校安全を考える~災害安全(防災)を中心に~」のテーマで、講演とワークショップを行っていただき、学校管理下における安全管理義務を履行するためには、ハザードマップ等地域の災害リスク情報等の把握および想定されるリスクへの事前対策等の準備が重要であることを解説していただき、問われうる責任についてもご紹介いただきました。
当日の模様は、日本損害保険協会の公式YouTubeサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。なお、小田先生には、高等学校の「地理総合」でハザードマップに関する学習が必須化されたことを踏まえ、高等学校の先生方向けに解説していただいた「ハザードマップを活用した地域の災害リスクを理解するための講習」(YouTube動画あり)にもご登壇いただいておりますので、あわせてご紹介いたします。
3.行政への働き掛け
(1)国土交通省・水管理・国土保全局長に要望書を提出(2023(令和5)年11月)
日本損害保険協会では、2023年11月28日に、防災・減災に資する実効性の高い施策のより一層の推進にむけて、国土交通省の水管理・国土保全局長に要望書を提出しました(同日、同省道路局長に対しても、交通事故防止に資する施策の実施に関する要望書を提出している)。
要望書においては、以下の内容を記載しています。
<国土交通省 水管理・国土保全局への要望内容(概要)>
| 要望項目 | 要望内容 |
|---|---|
|
1.流域治水の取組みの更なる推進 |
・「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす 流域治水の自分事化検討会のとりまとめの方向感を踏まえ、 国民の命、財産を守る観点からハード面・ソフト面の対策を 推進すること。 等 |
|
2.流域に関するデジタルデータの 提供・共有促進 |
・流域のあらゆる関係者の行動変容を促進するため、住民の避難 行動、行政による防災まちづくりや効率的な河川管理、迅速な 災害対応等に有益なデジタルデータの提供を推進すること。 等 |
|
3.水害リスクに関する情報提供の 更なる充実 |
・洪水ハザードマップ空白地域の解消に向け、令和 7 年度までに 約17,000 河川で洪水浸水想定区域図を作成するという目標が 達成されるような取組みの着実な推進、全国各地で発生して いる内水被害の低減に向けた地方公共団体への内水ハザード マップ作成支援の継続的な推進を実施すること。 等 |
|
4.持続可能なインフラメンテナンス の推進 |
・河川管理施設、下水道関連施設等の老朽化は洪水や土砂災害が 発生した際に正常に機能しないリスクがあるため、「予防保全」 への本格転換を通じた計画的な施設の維持管理・更新、新技術 の開発・導入による効率化・省人化、部品の規格・仕様標準化 や汎用品の活用等による持続可能なメンテナンスを推進する こと。 等 |
「防災・減災および交通事故防止に資する 実効性の高い施策のより一層の推進にむけて」~国土交通省 水管理・国土保全局および道路局に要望書を提出~
(2)洪水ハザードマップ空白地域の解消に向けて(2024(令和6)年3月)
日本損害保険協会では、地域の住民の方が災害発生後に向けた経済的な備えや、事前の防災・減災への手当てを講じる際、地域における各種災害リスクを確認することができるかが非常に重要と認識しています。
ここ最近、大きな被害をもたらしている水災害対策を講じるに際しては、「洪水ハザードマップ」の作成・公表が不可欠との認識から、普及促進・理解促進の取組みを進めてまいりました。
この間の普及の状況を確認するため、今般、全国の自治体における「洪水ハザードマップ」の作成・公表状況について、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」等に基づき、各自治体ホームページでの洪水ハザードマップの掲載内容等の確認を行いました。
その結果、全国の自治体1,749のうち、「洪水ハザードマップ」を作成・公表し、ホームページに掲載することを通じて周知していた自治体は1,576(90.1%)にのぼることがわかりました(調査時点:2024年2月末)。
なお、各自治体のホームページを確認していく中で、「洪水ハザードマップ」の作成・公表については、国土交通省、各都道府県がそれぞれのウェブサイトを通じて、各自治体へのアクセスを容易にする等創意工夫を重ね、積極的に後押ししていることも確認できました。
国土交通省は、令和3年3月末時点で1,365自治体が公表済と発表していましたので、この3年間で200超の自治体が新規に公表をしたことになります。また、15府県で管轄地域内の全ての自治体が「洪水ハザードマップ」を公表していることも確認しています。
当協会の調べでは、全国に「洪水浸水想定区域(国土交通省または都道府県が指定している洪水予報河川および水位周知河川が氾濫した場合に浸水が想定されるエリア)」が所在する自治体は1,428あり、うち1,422(99.6%)が「洪水ハザードマップ」等を公表済みとなっています。このように、水災害リスクの高いエリアをもつ自治体では、「洪水ハザードマップ」の整備がかなり進んでいる状況も確認しています。
調査結果の概要は、以下のとおりです。
【洪水ハザードマップ等の公表状況(全自治体ベース)】
| 調査項目 | 調査結果 |
|---|---|
|
◎洪水ハザードマップを公表済の自治体 |
・1,576自治体(全国1,749自治体の90.1%) |
|
◎管轄地域内の全自治体で公表済の |
・岩手県、山形県、栃木県、埼玉県、岐阜県、三重県、石川県、 富山県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県、 熊本県(15府県) |
|
◎ 同 95%以上の自治体で公表済の県 |
・宮城県、茨城県、千葉県、新潟県、愛知県、岡山県、広島県、 徳島県、佐賀県、長崎県(10県) |
【洪水ハザードマップ等の公表状況(水災害リスクの高いエリアベース)】
| 調査項目 | 調査結果 |
|---|---|
|
◎ 洪水浸水想定区域が所在する自治体 |
・1,428自治体(全国1,749自治体の81.6%) |
|
◎ うち、洪水ハザードマップを公表済 |
・1,422自治体 (洪水浸水想定区域が所在する1,428自治体の99.6%) |
|
◎ 洪水浸水想定区域が所在する全自治体 |
・青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、石川県、富山県、福井県、 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、 広島県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、 福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 (42都府県) |
全国1,576自治体が洪水ハザードマップをホームページで公表~自治体の公表状況を調査 ホームページで9割が掲載~
(3)「マイ・タイムライン」の普及拡大・理解促進に向けて(2024(令和6)年3月)
日本損害保険協会では、第9次中期基本計画で「災害に強い社会の実現」を掲げており、その取組みの一つとして「ハザードマップ」の普及促進を行っています。今般、自治体がハザードマップを活用して行う「マイ・タイムライン」作成研修の実施を推進する動画をYouTubeに公開しました。
「マイ・タイムライン」は、台風等の大雨による河川の水位上昇に備えるために住民一人ひとりが作成する防災行動計画です。作成にあたっては、自身を取り巻く洪水リスクを知り、どのタイミングで避難すべきかを検討するため、自治体が作成・公表した洪水ハザードマップを確認します。全国の自治体で「マイ・タイムライン」作成研修を実施いただき、同研修を通じて一人でも多くの方にハザードマップをご覧いただくことを企図して、本動画を制作しました。
本動画は、福島県須賀川市、国土交通省水管理・国土保全局、国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所、一般財団法人河川情報センターにご協力いただき、須賀川市で開催された自主防災組織向けの「マイ・タイムライン」講習会を取材した内容に基づいて制作しました。動画では、「マイ・タイムライン」作成研修を実施したい自治体が、研修がどのようなものかをイメージしていただけるように、実際の研修の流れや様子を収録しているほか、ハザードマップの活用方法について解説した当協会の動画コンテンツ「動画で学ぼう!ハザードマップ」も紹介しています。以下のURLからご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
「自治体向けにマイ・タイムライン作成研修の実施推進動画をYouTubeに公開」~ハザードマップの普及を目指して~
日本損害保険協会YouTubeサイト掲載動画・フルバージョン (10分31秒)
日本損害保険協会YouTubeサイト掲載動画・ショートバージョン (3分7秒)
(4)「江戸川、中川・綾瀬川流域治水協議会」に参画(2025(令和7)年5月)
日本損害保険協会 関東支部では、国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所が所管する江戸川、中川・綾瀬川の両流域治水協議会に「正委員(構成員)」として参画することになりました。
(ご参考)日本損害保険協会ホームページ 「協会各地の活動」-「関東支部の活動」
本協議会への参画を通じて行政機関との連携を強化し、各種啓発ツールの活用によるハザードマップの更なる周知やリスク啓発、被災後の経済的復旧の一助となる水災補償の必要性などを伝えることにより、地域のリスク認識と防災意識の向上ならびに水災を補償する損害保険の理解促進と普及向上に向けて鋭意取組んでいきます。
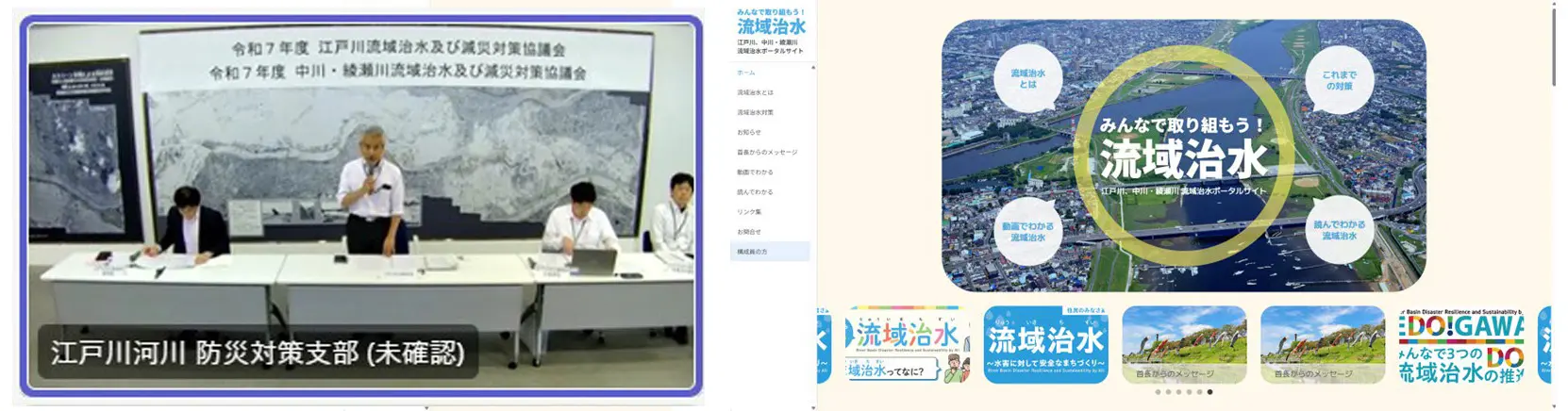
4.水防協力団体として「水防」活動を広報支援
(1)流域治水の自分事化検討会とりまとめの公表(2023(令和5)年8月)
激甚化・頻発化する自然災害から命を守り、被害を最小化するためには、住民や企業等が自らの水害リスクを認識し、自分事として捉え、主体的に行動することに加え、さらに視野を広げて、流域全体の被害や水災害対策の全体像を認識し、自らの行動を深化させることで、流域治水の取り組みを推進していく必要があります。
このため国土交通省では、令和5年4月に「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会(委員長 : 国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長 小池 俊雄、略称「流域治水の自分事化検討会」)」を設置し議論を重ね、住民や企業等のあらゆる関係者による、持続的・効果的な流域治水の取り組みの推進に向け、行動計画をとりまとめました。
水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会とりまとめ(2023年8月30日)
(2)「流域治水」への貢献と「水防」活動の支援
流域治水の自分事化検討会のとりまとめでは、「地域や流域を安全にすることが結果的に自社の安全や利益につながることを見える化する」、企業・団体等の流域治水への貢献を周知するための「地域に貢献する水防活動への企業等の参画」、「流域治水オフィシャルサポーター制度」の推進といった点が触れられており、「流域治水」と「水防」活動を一体的に推進することの必要性が指摘されております。
民間企業や団体、自治会、ボランティア団体等が「水防」活動を支援する枠組みとして、「水防協力団体」があります。「水防協力団体」は、水防管理者(市町村)の指定により、地域の「水防」活動に協力することができます。
流域治水の自分事化検討会のとりまとめを踏まえ、国土交通省は、同年12月、上記のように水災害被害低減には「水防」活動が欠かせない一方、「水防」活動を行う水防団員等の減少や高齢化が全国的に進んでおり、地域防災力の低下が懸念されていることから、その取組みをさらに支援・強化するため、募集の後押しを開始しました。なお、当協会を含めた各流域治水オフィシャルサポーター企業・団体等に対しても、「水防」の周知・啓発を支援する観点で、「水防協力団体」の指定申請を通じて協力して欲しい旨、呼び掛けが行われております。
国土交通省Web 「水防協力団体」として地域に貢献する企業等を募集しています!~水防団等が行う水防活動の後方支援やPR等のサポートをお願いします!~(2023年12月8日)
(3)「水防協力団体」指定と関係機関と連携した取組み
日本損害保険協会は、国土交通省の呼び掛けを受け指定申請を行い、2024(令和6)年1月11日、「水防協力団体」の指定を受けました。なお、「水防」活動に熱心に取り組んでいる淀川左岸水防事務組合からの指定を受けることができましたので、同地区の「水防協力団体」として同水防事務組合を窓口に「水防」活動の周知・啓発に協力してまいります。
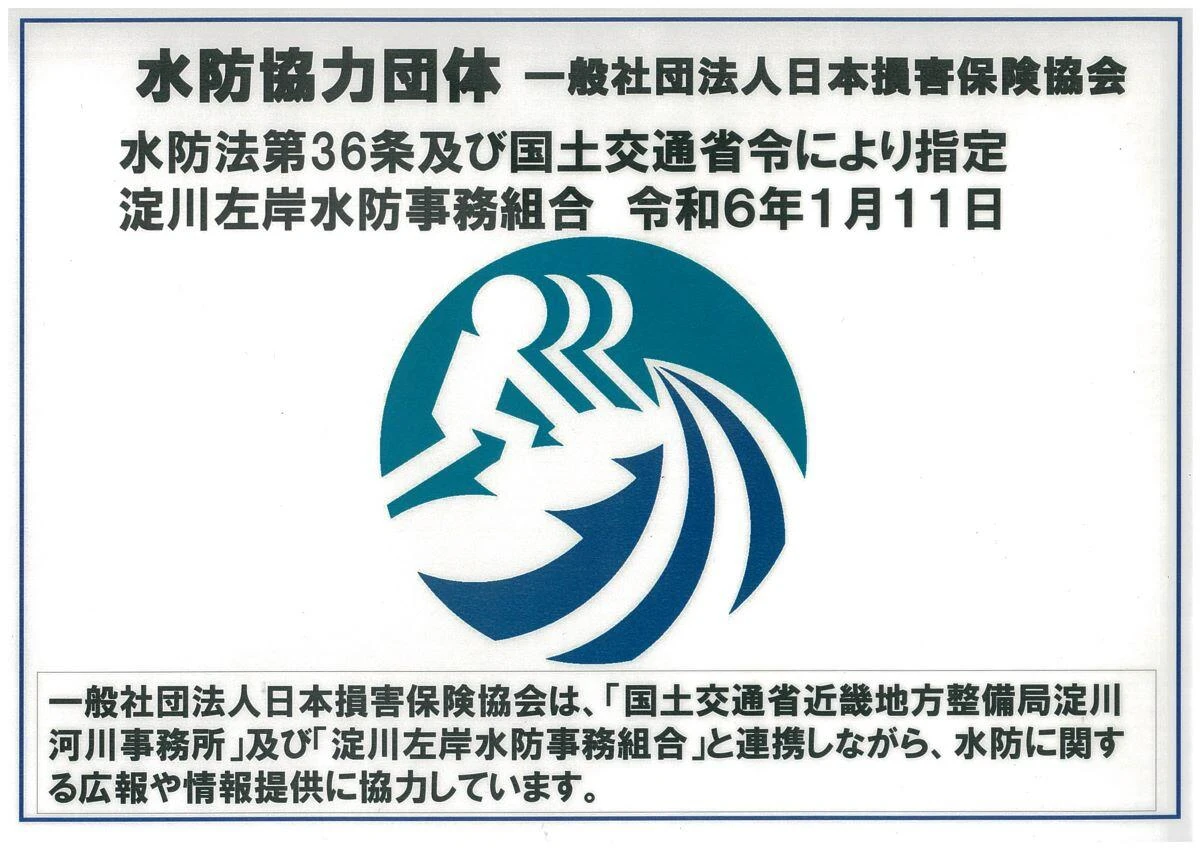
国土交通省Web 全国で12の企業・団体が新たに「水防協力団体」に仲間入り!~水防団の行う水防活動への協力を通じて、地域のために貢献する団体が増えます~(2024年3月15日)
【関連リンク】国土交通省の水災害による被害低減に向けた啓発サイト
国土交通省では、水災害による被害の低減に向けて、「ハザードマップ」「マイタイムライン」「水防」活動などに関して、様々な親しみやすい啓発のツールを作成しています。ご参考までいくつかのコンテンツをご紹介します。
きみの街にひそんでいる!気をつけ妖怪図鑑~高校生編~ (01:56)
子ども向け動画「水防団の神様 ~山からの知らせ~」(12:32)
マイ・タイムライン~災害時にとるべき行動計画~ (03:35)
出典 : 国土交通省Web「水管理・国土保全」サイトおよび各地方整備局「河川」サイト、(一財)河川情報センターWeb「防災情報の提供」
サイト
「防災・減災への取組み」の全体はこちら